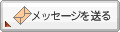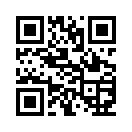2009年08月28日
セルフケアの手順
 ここでは、セサミオイルを用いたアーユルヴェーディック・セルフケアについて
ここでは、セサミオイルを用いたアーユルヴェーディック・セルフケアについて◆[オイルマッサージ用 セサミオイルのつくり方]
市販のごま油(生絞り)を用意します。日本では、炒ったごまを絞ってごま油を取るものと、生絞りの二種類があるようです。ここでは、後者の生絞りのごま油を使用します。消化には代謝という意味も含まれますが、皮膚を通して体内に入るごま油も、生のままでは吸収、消化がされにくくなると考えます。したがって、必ず熱処理をします。
①生絞りのゴマ油を深い鍋に移し中火にかけて、120℃までゆっくりと熱していきます。
その問はかき混ぜたりする必要はありませんが、油を扱っているので、火から目を離さないようにします。
②火を止めてしばらくそのまま 自然に放置し、冷めたら完成です。密閉ができるガラスの容器に移し替え、直射日光が入らない暗所で保管しておけば、夏でも室温での保存が可能です。こうしておけば、1年間はもちます。
市販されているアーユルヴェーディックオイルを使用するのもグッド!
◆解説
朝の洗い清めを終らせた後で、オイルマッサージをした方がよいです。食べてからマッサージをすることは、よくありません。また逆に、あまりおなかが空いているとき、すなわち、食事をとりたいという要求を強く感じているときにもオイルマッサージを行うことは、よくありません。
アーマすなわち未消化物という概念がアーユルヴェーダの病理学にあり、末消化物が溜っている病状の場合は、アビヤンガが禁じられています。熱病のあるとき、そして、アーユルヴェーダにおける浄化療法を受けた後、数日間もオイルマッサージをしてはいけません。
◆手順(ここでは、簡単な三点マッサージを紹介しましょう!)
『頭』
ⅰ)マッサージオイルを手のひらに適量(小さじ一~二杯)取る。
ⅱ)前中央で髪を分け、頭を下げて頭頂部の頭皮にオイルをつける。
ⅲ)髪の間に指を入れて、オイルが周囲に広がるように、指先の腹を使ってマッサージする。気持ちよく感じる強さの力で。
ⅳ)手のひらを置いた位置そのままでこすり、頭皮によくなじませる。
ⅴ)全体にオイルを行きわたらせるのが望ましい、あと一~二回オイルを手のひらに取って頭皮に塗り、指の方向をかえながら、全体をまんべんなくマッサージする。
『耳』
ⅰ)清潔にした指先にマッサージオイルをつけ、耳全体にオイルを塗ってマッサージする。
ⅱ)主として親指と人差し指を使い、耳の輪郭や耳たぶを引っ張ったり、さすったりする、耳のつけ根を人さし指と中指に挟んで上下させる動きも加えながら2~3分行う。中耳や鼓膜に異常のない人は耳の中にオイルを入れてから行うとよい。
『足』
注意:足の裏にオイルを塗った状態で立ち上がると滑ります。特に、浴室のぬれた床や浴槽内では転倒の危険がありますから、清潔なビーチサンダルかゴム草履を履いて行うことをおすすめします。
ⅰ)適量のオイルを手のひらに取りながら、足首から下の部分にくまなくオイルを塗る。
ⅱ)指の間も塗り残さないようにまんべんなく塗ることが大切。全体でオイルの量は小さじ二~三(十~十五cc)くらいあれば十分。
ⅲ)足の裏、足の中心から指先に向かって、両手の親指でしごくようにしたり、手のひらを足の裏全体にオイルをすり込む。かたくなっているところがあれば、もみほぐすようにする。足の指指の一本一本を引っ張ったり、前後に動かしたりする。指の間も、手の指を入れてオイルを浸透させるようにマッサージする。
ⅳ)足の甲、足全体を両手で包むようにして甲の中心に親指をあてがい、指先に向かってしごくようにさする。かかと、手のひらでかかとを包むようにし、丸く円を描きながらマッサージする。
おすすめポイント
*全身のリラクゼーションに足を刺激することで反射的に全身の緊張がほぐれ、予想外のリラックス感を得られる。特に目の疲れや視力の低下の回復に効果があり、パソコンなどで目を酷使する人にもおすすめ。
*不眠症、冷え症の改善に血行をよくしてからだを温める効果があり、就寝前に行うとぐっすり眠れる
古典では、マッサージするときの手の動き方について、はっきりした説明がありませんので、後にアーユルヴェーダの医師たちによって決められたことのようです。
筋肉の疲れが取れるように適当に圧力をかけて、オイルマッサージをすることはよいです。力を入れないで、軽くてのひらを動かすと、あまり効果がありません。あまり強く力を入れて、オイルマッサージを続けてやると、からだに痛みを感じる恐れがあります。だから、適度の圧力で、気持ち良くオイルマッサージするのが、正しい方法です。
他人にマッサージしてもらうことができれば効果が高いのですが、毎日アビヤンガを受けたい人の場合は、これは無理かもしれません。その場合は、自分でオイルマッサージをしても構いません。
◆後処理
最後にからだについている油を布で拭くか、豆の粉(チャナ=ひよこ豆または、米ぬか)でこすって取ります。きなこでもいいと思います。石鹸を用いると、毛穴の奥の油分も取れてしまい、完全に油が流されてしまうのでよくありません。布または豆の粉を使用したときは、皮膚の表面の油が取れても、毛穴の油まではなくならないのです。皮膚の衛生を考えて、清潔さを保つために必要とするときは、しっかり石鹸で洗うことも認められます。
オイルマッサージが終ってから、必ず入浴するか、シャワーで汗が軽く出るまでからだを温めることが必要です。耳に入れた油は温水浴が終ってから、きれいに取っておく必要があります。
◆注意事項(オイルマッサージをしてはいけないとき)
1 熱を出しているとき
2 食事の直後(消化が上手に行われないから)
3 あまりに太り過ぎている人(薬草粉末のペーストのマッサージが適用される)
4 生理中の女性(刺激を与えることになるのでやめておく)
5 妊娠中(妊娠していると分かったら、すぐにやめる)
6 体力があまりに消耗しているとき
Posted by 琉球アーユルヴェーダ at 11:35│Comments(0)
│オイルマッサージとは